-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
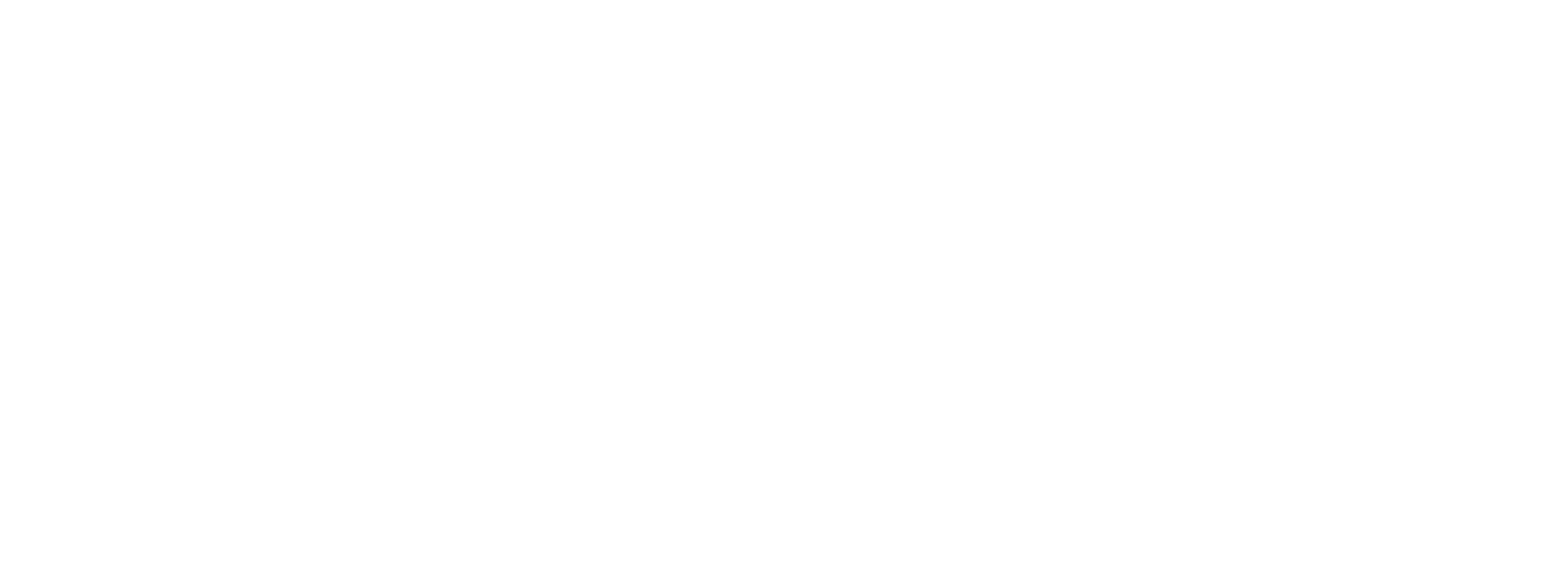
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
~“やりがい”~
① 社会インフラを支える誇り
工場の生産設備が動き続けるのも、ビルの空調やエレベーターが安全に運転できるのも、制御盤が正しく機能しているから。自分の仕事が社会の安定稼働に直結しているという責任感と誇りが大きなモチベーションです。
② 技術の奥深さを追求できる
電気回路、PLCプログラム、通信ネットワーク、熱設計、安全規格…。制御盤は「電気・機械・IT」が融合した領域であり、幅広い技術を吸収しながら成長できるのが魅力。📚💡
③ ものづくりの達成感
一台一台の盤はオーダーメイドが基本。設計から組立、試験を経て稼働した瞬間には、チーム全員での達成感があります。特に大型ラインの立ち上げで通電試験が成功する瞬間は格別。
④ 改善提案が形になる面白さ
盤内の配置改善で配線効率を高めたり、熱対策で寿命を延ばしたり、ソフト更新で操作性を上げたり…。自分のアイデアが製品や現場で活きる点も大きなやりがい。✨
⑤ グローバルに通用する技術力
制御盤はUL・IECなど国際規格対応が必須。世界中で共通に通用する知識や経験を積めるため、エンジニアとして市場価値が高まります。
A. 生産効率化・コスト削減
企業は競争力を高めるため、短納期・低コスト・高信頼性の盤を求めています。モジュール設計やE-CADの導入で効率化を実現できる人材・企業が評価されます。
B. DX・IoT対応
制御盤は単なるスイッチ箱ではなく、データを集約・通信する「情報ハブ」へ。IoTゲートウェイやリモート監視に対応した設計が強く求められています。📡
C. 機能安全・規格準拠
ISO 13849、IEC 62061などの機能安全規格、UL508AやIEC61439などの国際規格対応は必須条件。規格理解と安全設計力は業界での重要ニーズです。
D. 人材不足と技能継承
熟練技術者が不足する中、若手育成・標準化・デジタル教育が課題。現場では「多能工化」や「自律的に改善できる人材」が求められています。👷♀️
E. 環境・エネルギー対応
省エネ設計、再生可能エネルギー設備への対応、カーボンニュートラルを意識した部材選定など、環境配慮型の盤設計も新しいニーズに。🌱
エッジAIによる異常検知:盤自体が判断し、故障前に通知する未来。
デジタルツイン設計:3Dシミュレーションで熱・EMC・配線を仮想検証。
サブスク型サービス:盤を納めて終わりではなく、遠隔監視・保守契約で長期収益化。
人材多様化:電気だけでなくITやデータ解析ができるエンジニアの価値が上昇。
制御盤装置業は、社会を支える責任感、ものづくりの達成感、国際規格に通用する専門性といった大きなやりがいを持つ仕事です。
同時に、市場は効率化・DX・安全・環境配慮・人材育成といった多様なニーズを突きつけています。
まさに制御盤業界は「挑戦と進化のフィールド」。技術者一人ひとりの成長と改善提案が、未来の社会インフラを形づくっていくのです。⚡🌍
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
~“変遷”~
工場設備、ビル、インフラ、再エネ…あらゆる“動く仕組み”の心臓部が「制御盤」。その設計・製造・保全の在り方は、技術と産業構造の変化に合わせて大きく進化してきました。本稿では、制御盤装置業の変遷を技術・設計手法・規格・ビジネスモデルの観点から整理します。
技術の主役:電磁リレー・タイマ・カムスイッチ。
設計手法:紙面の回路図と職人の“手配線”。配線ダクトと番号チューブで美しく束ねる技能が価値。
特長:シンプルで堅牢。ただし変更に弱く、配線点数増で盤が大型化しやすい。
安全・規格:国内規格中心。安全柵・インターロックは機械式が主流。
技術の主役:PLC(シーケンサ)の普及で、リレー論理をプログラム化。
設計手法:回路最小化+I/O設計へ。盤は小型化し、改造・増設が容易に。
HMIの萌芽:ライト・7セグ表示→小型表示器へ。
品質・保全:自己診断・故障履歴が取りやすくなりダウンタイム短縮。
技術の主役:PROFIBUS、DeviceNet、CC-Linkなどのフィールドバス。
効果:I/O配線の削減、ノイズ耐性・診断性の向上、分散制御が一般化。
SCADA/上位接続:現場盤が情報を吸い上げ、監視PCと双方向通信。
設計の変化:アドレス設計・ネットワーク設計が盤設計の中核に。
技術の主役:タッチパネルHMI、産業Ethernet(EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT など)。
設計手法:モジュール化・ユニット設計が進み、UL508A・IEC規格対応が普遍に。
熱設計:高密度化で盤内温度管理(ファン・熱交換器・ダクト設計)が重要テーマに。
ドキュメンテーション:E-CAD(例:EPLAN)で回路・配線・部材表の一元管理が加速。
技術の主役:IoTゲートウェイ、クラウド連携、データ解析。
盤の役割:制御に加え状態監視(振動・温度・電流)、予知保全のデータハブへ。
セーフティ:ISO 13849 / IEC 62061 による機能安全(PL/SIL)設計。安全リレー・安全PLCの採用が常態化。
サイバーセキュリティ:リモート保守の普及でアクセス制御・暗号化が必須要件に。
技術の主役:エッジAIによる異常検知、**可変速ドライブ(VFD/サーボ)**の高度化、再エネ・蓄電池連携。
設計潮流:
超小型化:高密度端子・薄型ブレーカ・プラグインI/O。
デジタルツイン:盤の3D配置・熱流体シミュレーションで初期段階から品質を作り込む。
配電×制御の一体最適化:盤内短絡耐力・アーク対策、EMC設計の先回り。
規格・環境:IEC 61439、UL508A、RoHS/REACHなどグローバル対応が前提。
ビジネス:サブスク型遠隔監視、ライフサイクルサービスで“作って終わり”から“運用で稼ぐ”へ。
電源・配電:機器の省エネ化/直流化の活用、選択遮断・協調。
I/O層:スマートI/Oで配線削減、ホットスワップ対応。
通信:冗長化(RSTP、PRP)、セグメント分離でトラフィックとセキュリティ両立。
HMI/運用:アラーム哲学、OEE連動、操作手順の電子SOP化。
熱・EMC:初期段階からの熱設計・シールド・接地計画が歩留りを左右。
部材調達:半導体不足を契機に代替品評価・共通化が重要スキルに。
生産方式:セル生産+外注配線のハイブリッド、UL/CE検査の内製化。
人材像:回路・メカ・IT・安全規格にまたがる**“T型”から“Π型”エンジニア**へ。現場は多能工化。
モジュール設計(派生機種を高速展開)
デジタルエンジニアリング(E-CAD/BOM/熱解析の一気通貫)
機能安全+サイバーセキュリティの両立
遠隔監視サービスで継続収益を確保
グローバル規格適合とトレーサビリティの強化
**盤=“設備OS”**へ:制御・配電・データ・安全を束ねるプラットフォーム化。
エネルギーマネジメント連携:PV/ESS/EV との統合制御でピークカット・系統連携が標準に。
AI設計支援:自動配線計画・部品選定・発熱予測で設計の自動化が進行。
循環設計:再生プラ部材、リユース盤、ライフサイクルCO₂可視化などサステナブル対応が競争軸に。
制御盤装置業は、リレー時代の手配線からPLC・ネットワーク・IoT・エッジAIへと進化し、
小型・高密度
規格順守と安全性
データ駆動の運用価値
を同時に求められる産業へ。これからは設計〜運用〜保全をつなぐ“サービスまで含めた価値提供”が勝敗を分けます。
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
~“既設を生かして強くする”~
新規入替だけが正解ではありません。既設資産の再利用+部分アップグレードで、停止短縮・コスト最適化・省エネ・見える化を同時に達成できます。ここではレトロフィットの段取りとIoT/リモート監視・セキュリティの勘所をまとめます。🚀
現地調査:盤サイズ・ケーブル引込・端子番号・回路機能・配線ルートを全面写真+採寸。
互換部品選定:リレー→ソリッドステート、タイマ→PLC/リモートI/O、PLC旧機→現行CPU。
アダプタ板/DINレールで無加工化を狙う(穴位置流用)。
配線移設計画:端子No.を旧→新 対応表で作成、一括/段階切替を選択。
停止計画:夜間/休日、ライン分割で片系生産を維持。⏱️
I/Oマップ互換:アドレスは旧→新で一対一に。
命名規約:タグ名・コメント・版管理(Git/履歴)で「誰が見ても分かる」を徹底。
HMI:アラーム哲学(重要度/遅延/ラッチ)を整理、履歴と原因対策を残す。
バックアップ:CPU/SD/PCの三重。🗃️
容量・慣性マッチングを再計算。
制動抵抗/ブレーキの熱容量を再チェック。
EMC:新機は高周波ノイズが強いことも。フィルタ/シールド/グランドを最初から設計。🎧
電力量・デマンド・温度・振動をゲートウェイで収集→ダッシュボード化。
ファン/クーラはインバータ/温度制御で回し過ぎ防止。
アラームの“予兆化”:連続トリップ・温上昇・振動増加にしきい値+トレンドで先手。🔔
接続方式:VPN/ゼロトラスト等を採用、ポート開放は最小。
経路分離:**OT(制御)とIT(事務)**は物理/論理で分ける。
閲覧権限:役割ベース(RBAC)で閲覧・操作・管理を分離。
ログ:接続・操作・設定変更は全て記録し、改ざん防止。📝
資産台帳:コントローラ/スイッチ/アドレス/ファームを棚卸。
パッチ方針:適用窓口・検証→本番の二段階。緊急脆弱性は臨時適用ルートを用意。
USBメディア管理:スキャン・貸出台帳・持込禁止。
境界防御:ファイアウォール/IPS、不要サービス停止、強固なパスワード+多要素。🔐
電気図(単線・結線・I/O・端子・配線表)+ネットワーク構成図を最新版へ。
操作手順書/保守手順書に写真・動画QRを添付。
定期訓練:E-STOP誤作動・ネットワーク断・停電復旧の机上と実機。👩🏫
影響小→大の順に更新(例:I/Oカード→CPU→VFD)。
二重化期間(旧・新並走)を作り、スイッチオーバー試験でドライラン。
戻し手順(ロールバック)を紙で持つ。📄
停止時間・作業体制(夜間/休日、人数、資格)
アダプタ/配線再利用率(無加工・短工期の鍵)
試験範囲(FAT/SAT/予兆監視設定)
セキュリティ(VPN/権限/ログ/教育)
納品物(図面・プログラム・設定・写真台帳・バックアップ)
☐ LOTO(ロックアウト/タグアウト)実施
☐ 旧→新 端子対応表・I/O点検書
☐ VFD回転方向・ブレーキ試験
☐ 通信疎通(冗長/切替)・時刻同期
☐ アラーム哲学・しきい値設定
☐ 監視画面・履歴・ユーザ権限
☐ ロールバック手順・バックアップ三重
まとめ
“既設を生かす”レトロフィットד見える化・守る化”のリモート運用で、設備は強く・長く・安全に回ります。まずは**現地調査(写真+端子表)**から。最短ルートで設計をご提案します。🔧🌐🤝
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
~“止まらない盤”~
制御盤は現場の“心臓”。設計の段取りと部材・配線・熱・ノイズの4本柱を押さえるだけで、トラブルは激減します。この記事では要件定義→筐体設計→電源/保護→I/O→EMC→熱設計→検査まで、明日から使える実務の型をまとめました。
電源と負荷:一次電源(相・電圧・短絡容量)、非常電源の要否、VFD/サーボの台数。
安全レベル:非常停止・安全扉・ライトカーテン等。PL/SILの目標値と安全リレー/安全PLCの採用可否。️
環境条件:周囲温度/湿度/粉じん/油ミスト、屋内外、IP/IK等級、腐食雰囲気(食品・化学・海辺)。️
筐体選定:屋外や塩害はSUS/塗装鋼板+ガスケット、食品向けはR面・水切り形状。
ゾーニング:電源・動力・制御・通信を水平/垂直で分離。VFDはノイズ源ゾーンに。
余裕率:盤サイズは20〜30%の空きを目標(将来拡張・放熱)。
端子台:電源/アース/制御/フィールドを色別・列別で。保守は手前=現場、奥=装置内が鉄板。
主幹保護:遮断器は短絡容量・トリップ曲線を適合。二次側に漏電保護(用途に応じて)。
制御電源:DC24Vは二重化 or 冗長モジュール検討。サージ/雷保護も忘れず。⚡
セーフティ:E-STOPは自己保持回路+カテゴリ適合、双手操作/ガードは安全リレーで監視。
アース:一点接地の母線バーを用意。**保護接地(PE)と機能接地(FE)**は目的別に分ける。
入出力設計:DI/DO/AI/AOの点数+予備10〜20%。ノイズ源は絶縁型I/Oで距離を取る。
フィールド端子:端子台→フェルール端子で抜け防止。24V/0V/PEを3点セットで並べると現場が早い。
配線色(例):AC=黒/赤、DC+=赤、DC−=青、PE=緑黄、通信=灰/紫など、社内標準で統一。
通信:Ethernet/Fieldbusは金属ダクトから離して配線、曲げRを守り終端抵抗を適正に。
VFD/サーボ:RFIフィルタ・リアクトル、シールドケーブル360°接地。モータ側はアースクランプでがっちり。
ケーブル分離:電力>制御>通信の順に離す(最低でもダクト分離)。
避雷・サージ:SPD(クラス選定)を主幹→分岐→制御の順に多段。
グランドループ:一点接地+シールド片側接地を基本、必要に応じ両端接地+ドレインで高周波対策。
発熱計算:機器の損失合計→許容温度差から必要風量/クーラの能力を算出。
冷却手段:ファン/フィルタ→熱交換器→盤クーラの順で検討。フィルタ目詰まりの差圧監視が効く。
配置:上=発熱大、下=発熱小はNG。上=クーラ/ファン、下=吸気で流れを作る。
トルク管理:端子・ブレーカは規定トルクで。
結束:間隔=配線径の1.5〜2倍、熱源の近くは耐熱結束。
表示:機器ラベル・端子番号・ケーブルマーキングは同一書式で。QRで図面リンクも便利。
FAT(工場):回路絶縁・耐圧・I/Oシミュレーション・非常停止/インタロック。
SAT(現地):実機負荷・フィールドI/O・通信遅延・VFDの回転方向・安全機能の実動作。
記録:写真台帳+試験成績+設定バックアップを一式で納品。️
通信が不安定:電力線と同ダクト→ダクト分離・片側接地
盤内が熱い:クーラ容量不足→発熱再計算&風路見直し
E-STOPで止まらない:ロジック化→ハード有接点の安全回路へ
端子焼損:ゆるみ→定期トルク点検+ばね端子検討
☐ 主幹遮断器容量/短絡容量
☐ DC24V冗長/監視
☐ グランド母線/シールド処理
☐ VFDのEMC対策/シールド360°
☐ 放熱計算/差圧監視
☐ E-STOP/安全扉/カテゴリ試験
☐ I/Oマップ/予備点
☐ FAT/SAT記録・バックアップ
まとめ
ゾーニング×EMC×放熱×安全で“止まらない盤”に。まずはケーブル分離と放熱計算から手を付けるのが近道です。⚡
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
⚙️ 第10回 制御盤設計雑学講座
~小型化・省スペース設計の工夫~
今回は、制御盤設計における**「小型化・省スペース設計」**について掘り下げてご紹介します。近年の製造現場では、「省スペース化」は避けて通れないテーマ。限られたスペースの中に、必要な機能と性能を詰め込みながらも、安全性・保守性・拡張性をどう維持するかが、設計者の腕の見せどころです💪
制御盤の小型化が求められる背景には、次のような要因があります。
🏭 設置スペースの制限:省人化・自動化が進む中で、設備機器そのものがコンパクト化。制御盤にも同様の小型化が要求されます。
💸 コスト削減:設置スペースを減らすことで、工場の床面積あたりのコストが抑えられるメリットも。
♻️ 省エネ・省資源:素材やエネルギーの使用量を減らし、環境配慮型の設計へ。
⚙️ メンテナンス性の向上:適切なレイアウトにより、省スペースでも効率的な保守作業が可能になります。
⛓️ リレーやタイマーなどは、多機能一体型のコンパクト製品を選定することで、スペースを大幅に削減できます。
📶 通信や制御機器はPLCやリモートI/Oなどを活用し、複雑な配線を減らすことで、内部空間を有効活用できます。
部品は上下・左右・前後の空間を意識し、立体的にレイアウトを検討しましょう。
よく触る機器(ブレーカー・端子台など)は手前側に配置し、点検・交換作業がしやすい工夫も大切です。
据置型から壁掛け・棚設置タイプに変えるだけでも、全体の占有面積を圧縮できます。
ヒンジ式や引き出し式の構造を採用することで、狭い場所でも整備性を確保できます。
小型化の際に最も見落とされやすいのが熱対策です。
🔥 ファンレス設計でも熱がこもらないよう、熱源の近接配置を避ける。
💨 必要に応じて小型ファンや換気ルーバーの追加で、熱を外に逃がす工夫が必要です。
📊 熱シミュレーションや温度モニタリングシステムを用いることで、設計段階から熱問題に対応できます。
ある中規模工場では、既存の制御盤が幅1800mm・奥行600mm・高さ2000mmという大型サイズで、現場スペースを圧迫していました。小型化設計を導入し、以下のように改善:
PLCやインバーターなどの省スペース機器に統一
制御部をモジュール化してユニット単位で配置
放熱対策として自然対流構造の設計を導入
その結果、盤サイズは約30%縮小しつつ、配線の整理によりメンテナンス時間を20%短縮することに成功しました✨
制御盤の小型化は、ただサイズを削ることではありません。「限られたスペースに最大限の価値を詰め込む」ことが、本当の意味での省スペース設計です。
そのためには、使用環境・機器特性・保守性のすべてを見極め、設計思想から見直す柔軟な発想が求められます。
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
🔌 第9回 制御盤設計雑学講座
~配線の基本とトラブルを防ぐ配線設計術~
今回のテーマは、制御盤設計における“見えないけれど超重要”な部分、配線についてです。制御盤の中身を開けたとき、ケーブルが整然とまとめられていると、それだけで「プロの仕事だな」と感じられるものです。しかし、配線設計は単なる見た目の問題ではありません。誤作動の防止・メンテナンス性・安全性・コスト効率など、あらゆる要素に影響する“設計の質”を左右する要素なのです。
制御盤の配線を考える際にまず大切なのは、機能と目的に応じた設計です。信号線、電源線、アース線、それぞれの役割を正しく理解し、干渉やノイズのリスクを最小限に抑えるルーティングが求められます。
たとえば、DC24Vの制御線と200Vの電源線を同一ルートに束ねてしまうと、誘導ノイズによる誤作動や通信トラブルの原因になることも。配線の「分離」「交差」「距離の確保」は基本中の基本です。
使用するケーブルは、電圧・電流・伝送距離・設置環境(耐熱、耐油、可とう性など)を考慮して選定します。
制御線:IV線やVCTFなどが一般的。柔軟性が求められる場所では耐屈曲性の高いケーブルを使用。
電源線:大電流を流す場合は、CVやCVVなどを選定。
信号線/通信線:ツイストペアやシールド付きケーブルを用いて、ノイズ対策を強化。
また、線番表示(マーキング)も保守性に大きく影響します。あらかじめ「どの信号がどの端子につながるのか」を把握しやすくすることで、点検や故障対応の時間を大幅に短縮できます。
配線ルートは、盤内の温度や風通しも意識して設計することが重要です。熱源の近くを避け、ケーブルが自然に弛まない程度の適切なテンションでまとめるのが理想。固定には、インシュロック(結束バンド)だけでなく、ダクトや配線モール、ステップルなども活用して整然と配置しましょう。
さらに、メンテナンス性を意識した「分割可能なルート設計」もおすすめ。たとえば、将来的に機器を追加することが想定される場合は、予備のルートや空きスペースを残しておくと柔軟に対応できます。
配線不良によるトラブルは、制御盤トラブルの中でも頻出の原因です。以下のようなミスを避けることで、事故や誤動作のリスクを大幅に軽減できます。
圧着不良や端子の緩み → トルク管理と目視確認
絶縁不良 → スリーブ・チューブで補強
過大電流 → 適切な太さのケーブル選定と保護ヒューズ
配線ルートの混線 → 系統別でダクトを分ける
また、完成後の絶縁抵抗測定・導通試験を実施しておくことも重要な工程です。
配線設計は、単に「線をつなぐ作業」ではありません。設計者の意図・知識・現場の配慮が詰め込まれた、制御盤の“完成度を左右する要”とも言える工程です。
整然とした配線はトラブルを防ぎ、メンテナンス性を高め、そしてなにより「安心と信頼」を生み出します。制御盤設計のプロフェッショナルとして、一つ一つの線に責任と技術を込めて設計していきましょう!
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
本日は第8回制御盤設計雑学講座!
さて今回は
~鉄則~
ということで、制御盤設計における鉄則を詳しく解説し、プロフェッショナルな設計者が守るべきポイントを深く掘り下げます♪
制御盤は、工場・プラント・発電所・インフラ設備などで機械やシステムを制御するための重要な装置です。適切に設計された制御盤は、機器の安定動作・作業の効率化・メンテナンス性の向上・安全確保を実現します。しかし、制御盤の設計を誤ると、機械の誤動作・火災・感電事故・システムダウンなど、重大なトラブルにつながる可能性があります。
制御盤を設計する際には、以下の3つの基本方針を常に意識することが重要です。
安全性(Safety)
機能性(Functionality)
メンテナンス性(Maintainability)
制御盤内部の配置設計は、発熱・配線の取り回し・メンテナンスのしやすさを考慮して行う必要があります。
🔹 発熱対策
🔹 配線ルートの確保
🔹 メンテナンス性の確保
制御盤に供給される電源は、機器の種類や使用環境に応じて最適に設計する必要があります。
🔹 電源の基本設計
🔹 過電流・短絡対策
工場やプラントでは、インバーター・モーター・高圧機器などが発生する電磁ノイズが制御盤に悪影響を与えることがあります。ノイズ対策を怠ると、誤動作や信号異常が発生するため、しっかり対策を講じることが重要です。
🔹 ノイズ対策の基本
制御盤は長期間使用する設備であるため、メンテナンスのしやすさが非常に重要です。
🔹 保守性を向上させる工夫
近年、IoT・AI・クラウド技術を活用した制御盤が増えています。これらの技術を導入することで、効率的な運用やトラブル予測が可能になります。
🔹 最新技術の活用ポイント
制御盤設計における鉄則を守ることで、安全で効率的なシステムを構築することができます。
最新技術を活用しながらも、基本的な設計ルールを守ることが、信頼性の高い制御盤を作る鍵となります。
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
本日は第7回制御盤設計雑学講座!
さて今回は
~歴史~
ということで、制御盤設計の歴史と背景について深く掘り下げ、その進化が産業技術にどのような影響を与えてきたのかを解説します♪
制御盤は、電気設備や機械の動作を管理・制御するための装置であり、産業界において不可欠な存在です。歴史的には、手動スイッチから始まり、リレー制御、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)、そしてIoT・AI技術を活用したスマート制御へと進化してきました。
制御盤の歴史は、19世紀後半の電気技術の発展とともに始まりました。それまでの工場の機械制御は、蒸気エンジンや水力を利用したベルト駆動システムが主流でしたが、電気が導入されることで、より精密な制御が可能になりました。
20世紀初頭には、電磁リレーを利用した制御システムが登場しました。リレーは、電気信号のON/OFFを制御するスイッチとして機能し、産業機械の自動化を促進しました。
この時期の制御盤は、大量のリレーを用いて機械の動作を順番に制御するものであり、回路設計が複雑になると配線ミスやトラブルが増えるという課題もありました。
1960年代になると、リレー制御の複雑化によるメンテナンスの手間や誤作動のリスクが問題視されるようになりました。この課題を解決するために、電子回路を活用した制御装置が開発されました。
PLCの特徴は、プログラムによる制御の変更が可能なことです。リレー制御では回路を変更するたびに配線を組み替える必要がありましたが、PLCならソフトウェアを書き換えるだけで制御内容を変更できるため、製造業の生産ラインの柔軟性が飛躍的に向上しました。
1980年代になると、PLCの処理能力が向上し、アナログ信号の処理やセンサーとの連携が可能になりました。これにより、温度・圧力・流量などの制御もPLCで行えるようになり、火力発電所・石油化学プラント・自動車工場などの大規模システムにも導入されるようになりました。
1990年代には、制御システムがさらに進化し、PLCとコンピュータを連携させたSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)が登場しました。
2000年代に入ると、PLC同士や上位システムとの通信にEthernet(イーサネット)が導入され、制御盤のネットワーク化が加速しました。
これにより、大規模な発電所や化学プラントでは、遠隔地からのモニタリングや自動調整が可能になりました。
2010年代以降、IoT(モノのインターネット)技術が制御盤にも導入されるようになり、リアルタイムデータの活用が進んでいます。
現在では、AIとIoTを組み合わせたスマート制御盤が開発され、以下のような機能が実現されています。
制御盤設計は、手動操作→リレー制御→PLC→ネットワーク化→スマート制御という形で進化してきました。
今後も、AI・5G・クラウド技術と融合しながら、より高度な自動化と効率化を実現する制御盤の進化が期待されます。
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
本日は第6回制御盤設計雑学講座!
今回は、海外の制御盤設計の資格と特徴についてです。
制御盤設計は、工場の生産設備や発電所、輸送システム、ビルの管理システムなど、さまざまな産業で必要とされる重要な技術です。特に海外では、国や地域ごとに産業規模や技術レベルが異なるため、制御盤設計に関わる資格も多種多様です。国際的に通用する技術力を証明する資格を取得することは、キャリアアップやグローバルな職場での活躍において重要な鍵となります。本記事では、海外における制御盤設計に関連する主要な資格とその特徴について深く掘り下げ、それぞれの資格がどのように産業界で求められているかを解説します。
制御盤は、産業機械や設備の動作を制御・監視する「頭脳」の役割を果たします。これを設計する技術者は、電気工学、制御理論、安全基準など幅広い知識が求められるため、資格による専門性の証明が極めて重要です。特に海外では、以下の理由から資格が求められています。
CCSTは、アメリカの**ISA(International Society of Automation)**が認定する資格で、制御システムに特化した技術者を対象としています。
TÜV Rheinlandが提供するFunctional Safety Engineer資格は、機能安全に特化したエンジニアの認定資格です。制御盤設計においては、特に安全性を重視する分野で必須とされています。
カナダで認定される**CET(Certified Engineering Technician)**資格は、電気、電子、機械分野の技術者を対象とした資格で、制御盤設計にも関連性が高い資格です。
EASA(European Aviation Safety Agency)の資格は、航空分野での電気技術者向けに提供されるものですが、産業分野でも適用可能な広範な知識を含んでいます。
CEEは、制御盤設計に必要な電気工学の知識を持つことを証明する国際資格で、特に多国籍企業やグローバルプロジェクトで評価される資格です。
海外で認知された資格は、技術者としての専門性を公的に証明し、企業や顧客からの信頼を得るための重要な要素となります。
国際的に評価される資格を持つことで、多国籍企業や海外プロジェクトでのキャリアチャンスが広がります。
資格保有者は、その専門知識が評価され、高収入ポジションや管理職に就くチャンスが増える傾向があります。
まとめ 海外における制御盤設計関連の資格は、国際規格や技術要件に準拠したスキルを証明する手段として重要な役割を果たしています。CCST、TÜV Functional Safety Engineer、CET、EASA資格、CEEなど、各資格はそれぞれの地域や産業に特化したスキルを証明し、技術者としての信頼性を高めます。グローバルなキャリアを目指す技術者にとって、これらの資格を取得することは、専門性を磨き、新たなチャンスを掴むための大きな一歩となるでしょう。
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
新年あけましておめでとうございます
今年もどうぞよろしくお願いいたします
本日は第5回制御盤設計雑学講座!
今回は、制御盤設計の資格と特徴についてです。
制御盤設計は、産業機械や設備の心臓部ともいえる重要な分野です。制御盤とは、電気設備や機械の動作を監視・制御するための装置であり、製造業、発電所、ビル管理など、さまざまな分野で必要不可欠な存在です。これを設計する技術者には、高度な知識とスキルが求められるため、関連する資格を取得することがプロフェッショナルとしての能力を証明し、キャリアを築く大きな鍵となります。本記事では、制御盤設計に関する主な資格とその特徴について深く掘り下げ、技術者が持つべきスキルや資格取得のメリットについて解説します。
制御盤設計は、現代の工業生産において重要な役割を果たします。電気回路の設計や部品選定、制御プログラムの開発など、幅広い知識と経験が求められます。資格を取得することは、こうした技術を公式に証明し、信頼性を高めるための手段です。
制御盤設計に関連する資格は多岐にわたり、それぞれが異なるスキルや専門性を証明します。以下は、制御盤設計において特に重要とされる資格の例です。
電気主任技術者は、電気設備の運用・保守・管理を行うための国家資格で、制御盤設計にも深く関わる知識が求められます。
電気工事士は、電気設備の設置や配線工事を行うための国家資格です。制御盤設計者として配線設計や施工の知識が求められる場合、この資格が役立ちます。
計装士は、プラントや工場の制御システムに関する設計や運用を担う技術者を対象とした資格で、制御盤設計においても重要です。
制御盤設計には、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を用いた制御ロジックの設計が不可欠です。各メーカーが提供する資格プログラムは、実践的なスキルを証明する手段となります。
技術士は、科学技術全般における高度な専門知識を持つ技術者を認定する国家資格で、制御盤設計においても特に上級者向けの資格といえます。
制御盤設計に関連する資格を取得することで、多くのメリットが得られます。
資格を持つことで、自身の専門性を公的に証明することができます。これにより、顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。
資格を取得することで、設計業務だけでなく、プロジェクト管理や技術指導といった上級職に就くチャンスが増えます。
資格保有者は、その専門性が評価されるため、給与面での待遇が向上する可能性が高まります。
資格取得を目指す学習過程で、最新の技術や規格について知ることができ、技術者としての成長につながります。
まとめ 制御盤設計は、現代の産業の基盤を支える重要な技術分野であり、そのプロフェッショナルになるためには、適切な資格を取得することが欠かせません。電気主任技術者、電気工事士、計装士、PLCプログラマ資格、技術士など、それぞれの資格は異なる専門性を証明し、キャリアアップの道を開きます。資格取得を通じてスキルを磨き、現場での信頼性を高めることで、制御盤設計者としての未来はさらに広がるでしょう。
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()