-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
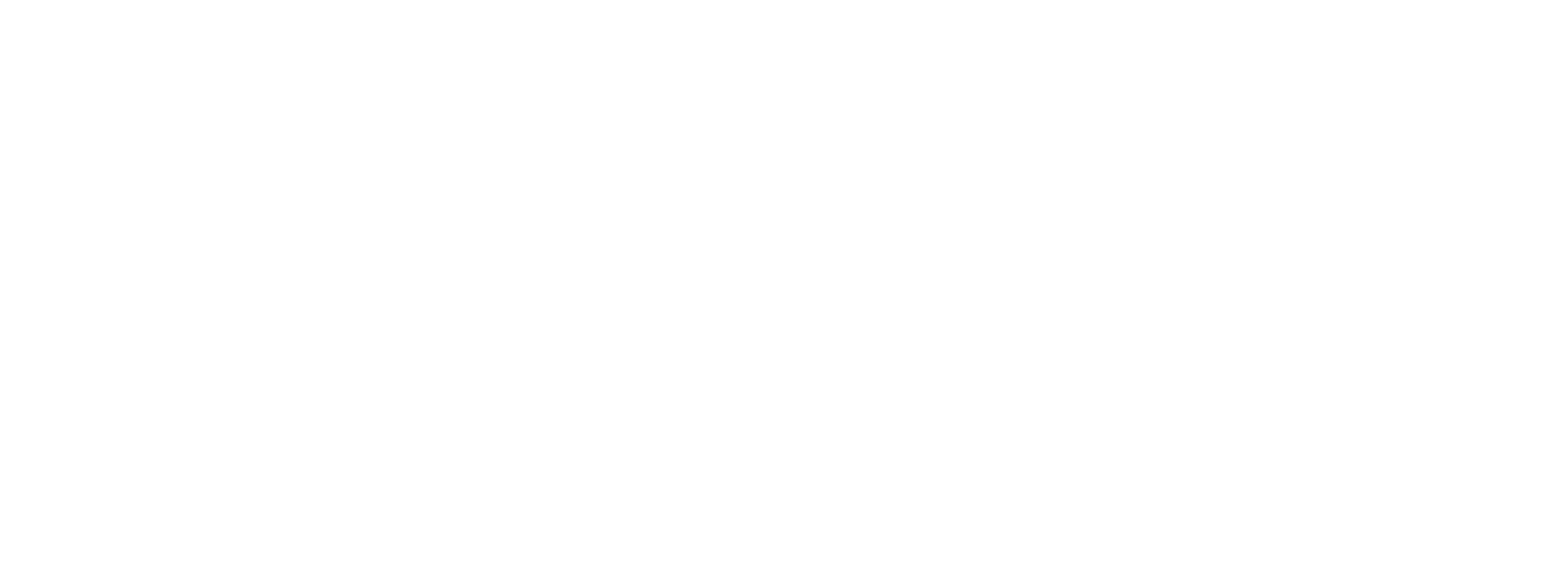
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
本日は第4回制御盤設計雑学講座!
今回は、制御盤の施工についてです。
制御盤の施工~設置と最終確認
製造が終わった制御盤は、いよいよ実際の産業機械に設置する「施工」の段階です。
この工程では、制御盤を現場に設置し、機械と連携させて正常に稼働できる状態にします。
1. 設置場所の確認と固定
制御盤は、その場所に適した設置が必要です。
湿気や振動が多い現場には防塵や防水のケースが必要ですし、安定した場所に固定して、予期せぬトラブルが発生しないようにします。
設置後は地震などでの倒壊が起こらないようにしっかりと固定します。
2. 配線と接続の確認
制御盤と産業機械を接続する際は、全ての配線が図面通りに行われているか確認し、配線の緩みや接触不良がないように慎重にチェックします。
特に電源線や信号線は、機械の動作に直接影響するため、正確に接続されていることが重要です。
3. 最終動作確認と安全検査 設置が完了したら、最後に動作確認を行います。
機械全体が制御盤の操作に従って正確に動作するか、緊急停止ボタンなどが正常に機能するか、細かく確認します。
これにより、安全面での問題がないことを最終的に確認して施工が完了します。
以上、第4回制御盤設計雑学講座でした!
次回の第5回もお楽しみに!
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
本日は第3回制御盤設計雑学講座!
今回は、制御盤の製造についてです。
制御盤の製造~高い精度と品質管理が求められる
製造は、設計図や製図に基づいて制御盤を組み立てていく工程です。
製造の工程でのミスがシステム全体に影響することがあるため、正確さと高い品質管理が求められます。
1. 配線の正確な取り付け
配線作業では、設計図に従い、指定された場所に配線を取り付けていきます。
配線が混乱しないように、ケーブルの色や番号で管理し、取り付け位置や接続先が正しいか慎重に確認しながら進めていきます。
また、配線がきれいに整理されていることで、万が一のメンテナンス時に作業がしやすくなります。
2. 部品の取り付けと固定
制御盤に取り付ける部品(端子台やリレーなど)は、振動や衝撃に耐えられるように確実に固定します。
ネジの締め忘れや取り付け位置のずれがないよう、各部品がしっかりと取り付けられているか確認します。
特に、ブレーカーやリレーは安定性が求められるため、適切に固定されていることが大事です。
3. 品質管理と動作確認
完成した制御盤が設計通りに動作するか、実際に通電して確認します。
通電テストや操作テストを行い、スムーズに動作するか確認した後、安全性の検査を行います。
この検査で異常があれば、原因を追究し、問題が解決するまでテストを繰り返します。
以上、第3回制御盤設計雑学講座でした!
次回の第4回もお楽しみに!
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
イベント盛り沢山なこの季節、いかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は第2回制御盤設計雑学講座!
今回は、制御盤の製図についてです。
制御盤の製図~精密な図面作成の重要性
設計で構想が練られたら、次に製図を行います。
製図は、制御盤を形にするための具体的な指針を示すもので、製造・施工を正確に行うための「設計図」でもあります。
製図がしっかりしていることで、後の製造工程がスムーズに進むだけでなく、製品の品質も高まります。
シンボルと記号の正確な使用 制御盤には、リレーやスイッチ、ブレーカー、端子台など多くの部品が使われます。
製図では、それぞれの部品に対応するシンボルや記号が正確に記載され、わかりやすく配置されている必要があります。
こうした統一された記号の使用によって、製造や施工スタッフが理解しやすい図面が完成します。
部品配置と配線経路の最適化 制御盤の内部はスペースが限られているため、部品の配置や配線経路が重要です。
耐熱性やメンテナンス性も考慮しながら、部品を効率よく配置し、配線が重ならないように設計します。
これによって、制御盤の中での熱が分散され、部品の寿命が延び、安定的な動作が可能となります。
図面の精度とチェック作業 図面が正確であることは、制御盤の品質に直結します。
配線ミスや配置ミスが発生しないように、製図段階でしっかりと見直しを行い、何重にもチェックします。
図面に誤りがないか、部品の選定や配線の順序に無理がないかを確認することが大切です。
以上、第2回制御盤設計雑学講座でした!
次回の第3回もお楽しみに!
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ツバサオートメーション、更新担当の中西です。
いよいよ寒くなってきましたが、皆さん元気に過ごされていますか?
風邪をひかないよう、防寒対策を徹底していきましょう!
さて、本日からシリーズ更新が始まります!
株式会社ツバサオートメーション監修!
記念すべき第1回目のテーマは!
制御盤の設計は、産業機械や設備が安全かつ効率的に稼働するための「頭脳」を作る作業です。制御盤がシステムの心臓部となり、各パーツやシステムをコントロールしているため、設計段階での細かな配慮が非常に重要になります。
仕様の確認と要件定義
まずはお客様のニーズを把握し、システム全体がどう機能すべきかを確認します。例えば「どのような動きをする機械か」「安全性はどのくらい必要か」「稼働する環境の温度や湿度」などを確認していきます。これらの要件に基づき、制御盤が持つべき機能や性能を具体化し、図面に落とし込んでいく作業を行います。
回路設計と部品の選定
次に電気回路を設計します。機械の動作に必要な電流や電圧に応じて、最適な配線構成を考えます。また、使用する部品の信頼性や寿命を考慮し、定格に合った部品を選定していきます。制御盤に使われる部品には、耐久性が求められるため、部品メーカーの選定や適切な材料の選び方もポイントです。
安全対策と冗長性の確保
産業機械は、常に安全が最優先です。たとえ一部のシステムが故障しても、安全に動作を止めることができるように「冗長性」を持たせます。例えば、センサーやブレーカーを複数設置することで、安全に稼働を続けられるようにし、万が一の故障にも備えます。こうした安全対策は、設計段階で計画的に行う必要があります。
以上、第1回制御盤設計雑学講座でした!
次回の第2回もお楽しみに!
株式会社ツバサオートメーションでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()